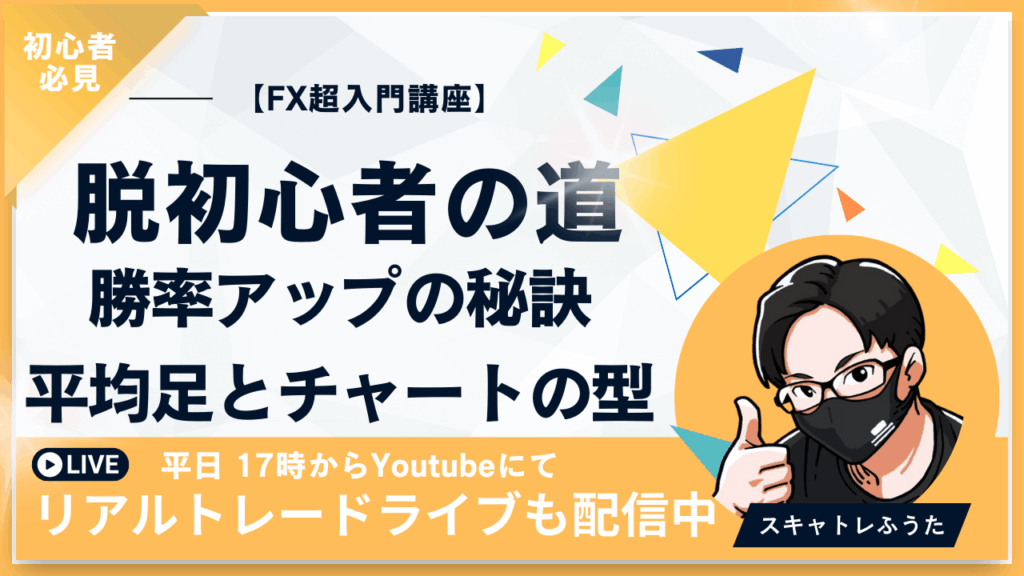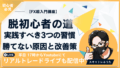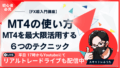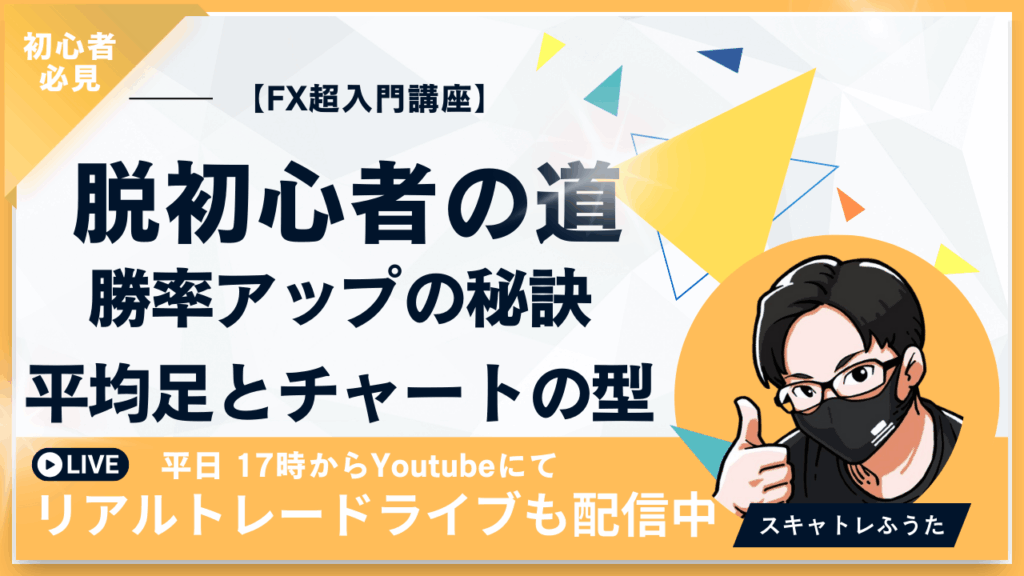
スキャルピングをしていて「どこで入ればいいかわからない」「なんとなくエントリーして負けてしまう」という悩みは多くの方が経験する壁です。私自身も初心者の頃、似たような失敗を繰り返していました。
しかし、平均足とチャートパターンを正しく使うようになってから、トレードの質が劇的に変わったのです。特に、直近の高値・安値の意識、そしてダブルボトムや高値切り下げなどの定番パターンの活用は、相場の流れに沿ったエントリーを可能にします。

この記事では、これらのノウハウを段階的にわかりやすく解説していきます。最初はうまくいかなくても、手法の本質を理解し、実践で繰り返すことで精度が高まっていきます。
それでは具体的な内容を見ていきましょう。
これからFXを始める初心者に観てほしい動画です。
平均足の色変化でエントリータイミングを見極める
平均足の3本目が伸びやすい理由と活用法
スキャルピングにおいて、平均足の色変化はエントリー判断の重要な材料となります。特に注目すべきは、平均足の「3本目」です。この3本目は相場の方向性が確定しやすく、勢いに乗りやすいため、短期で利益を狙うには絶好のタイミングといえるでしょう。
なぜ3本目なのかというと、1本目でトレンド転換の兆候が現れ、2本目でその動きが強まることで、3本目では市場の参加者が本格的に流れに乗ってくるからです。その結果、トレンドが加速しやすく、伸びのあるローソク足が出やすいという特徴があります。
私自身も、例えばダブルボトム形成後に平均足が青に切り替わり、3本目が出現したタイミングでロングを仕掛けるようにしています。逆に、赤に変わった場面ではショートに切り替えることで、トレンドの流れに乗る確率が高まります。
平均足の色変化を見逃さず、3本目の動きをしっかり観察することで、感覚に頼らないエントリーが可能になります。これは再現性の高い判断基準となるため、初心者にも特におすすめしたい手法です。
逆ひげ・実体の動きから方向感を読む方法
平均足の「色」だけでなく、「ひげ」と「実体」の形状も相場の方向感を読む上で欠かせない要素です。特に逆ひげ(下方向に長いひげ)が目立つ場面では、反発のサインとして機能することが多く、次の平均足の動きと組み合わせることで、トレードの精度が一段と高まります。
逆ひげは、下落の勢いがいったん止まり、買い勢力が反撃に出た証と解釈できます。そのため、逆ひげの次に平均足が青に変わった場合、トレンドの切り替わりが始まる可能性が高いのです。反対に、上方向に長い逆ひげが出て赤に変わる場面では、売りの圧力が強まっていると判断できます。
私が実際にエントリーする際は、逆ひげと平均足の色変化が重なるポイントを重視しています。例えば、高値圏で逆ひげと赤の出現が重なった場合、売りの勢いが出る前兆と見てショートを狙うことが多いです。

こうした逆ひげや実体の動きは、視覚的にも分かりやすく、慣れてくるとリアルタイムで判断がしやすくなります。平均足を「見るべき場所」で見ることが、スキャルピングの勝率を大きく左右します。
直近の高値・安値にラインを引いて狙いを明確にする
ラインの引き方とエントリーポイントの選定
トレードで勝ち続けるためには、感覚的なエントリーをやめて、「狙うポイント」を事前に明確にしておくことが不可欠です。そのための基本が、直近の高値・安値にラインを引くという作業です。
なぜこれが重要なのかというと、相場は過去の価格帯で反応しやすく、特に直近の高値・安値は多くのトレーダーが意識する水準だからです。こうしたラインは、相場の“折り返し地点”や“突破口”になりやすく、次の値動きを読む基準となります。
私も普段のチャート分析では、1分足の中でも明確な高値・安値を基準に水平線を引き、その少し手前でエントリーの準備をしています。実際にラインにタッチしたからといって即エントリーするのではなく、その前後の動きやチャートパターンを確認することで、より根拠のある判断ができます。

まずは自分でラインを引いてみること。それだけでも相場の見え方が大きく変わってきます。ラインが引けるようになると、どこで待ち構えるべきかが明確になり、無駄なエントリーも自然と減っていきます。
水平線と上位足の節目を重ねて精度を上げる
1分足だけでラインを引いても、トレンド全体の流れを読み違えると失敗につながります。そこで重要になるのが、「上位足の節目」と自分の水平線を重ねて見るという視点です。
なぜなら、上位足の節目はより多くの市場参加者が注目する価格帯であり、そこに短期足のラインが重なると、反発やブレイクの信頼度が一気に高まるからです。
具体的には、以下のような上位足の情報が重なっているかを確認しています。
- 5分足のミドルライン(移動平均線)
- 15分足のボリンジャーバンド−2σや+2σ
- 4時間足以上のサポート・レジスタンスライン
私自身も、水平線を引いたあとに上位足チャートを切り替え、これらの節目と重なっているかを毎回チェックしています。特に、複数の根拠が重なるポイントでは、エントリーの精度も高まり、決済までの流れも読みやすくなるでしょう。
反対に、上位足と重なっていないラインでは見送りを選ぶこともあります。判断に迷う場面であっても、重なるかどうかという明確な基準があることで、冷静にトレード判断ができるようになります。

このように、短期足のラインに上位足の根拠を加えることで、より堅実なエントリーが可能になります。トレードの精度を一段階引き上げるためにも、ぜひ意識してみてください。
チャートパターンを組み合わせて根拠あるエントリーを行う
ダブルボトム・ダブルトップを活用する
チャートパターンの中でも、ダブルボトムとダブルトップは非常に汎用性が高く、エントリーの根拠として優秀です。特にスキャルピングでは、反転の初動を捉える精度が重要になるため、これらのパターンを見逃さずに捉えることで勝率を大きく上げることができます。
ダブルボトムは、下落の流れから2度目の安値で反発が起きる形で、トレンド転換のシグナルと見なされます。逆に、ダブルトップは上昇の流れが一服し、売りが優勢になるサインとして活用されるでしょう。
私も実際に、ダブルボトムの2回目の安値で反発を確認し、平均足が青に変化したタイミングでロングエントリーするパターンを多く使っています。反対に、ダブルトップで高値を超えられず、平均足が赤に変わった局面では、ショートを狙うことが多いです。

こうした定番パターンを丁寧に観察することで、感情ではなくチャートの形に基づいたエントリーができるようになります。
安値切り上げ・高値切り下げのトレンド転換サイン
トレンドの転換を早期に捉えるためには、「安値の切り上げ」や「高値の切り下げ」といった価格の動きに注目することが有効です。これらの動きは、次のトレンド方向への勢いが生まれる前兆として機能するからです。
たとえば、安値を切り上げたあとに平均足が青に変化すれば、上昇トレンドへの転換を示唆します。逆に、高値を切り下げて平均足が赤に変われば、下降トレンドの初動である可能性が高まります。
私が普段意識しているのは以下のようなポイントです。
- 切り上げ・切り下げが明確な形で視認できるか
- 前の山や谷に対して、しっかり角度がついているか
- 平均足の色変化と同時に発生しているか
これらが揃っている場面では、トレンド転換の信頼度が高く、優位性のあるエントリーポイントになります。特に初心者の方は、明確な「切り上げ・切り下げ」の形を狙っていくことで、判断に迷わないトレードができるようになるでしょう。
トリプルボトム・トリプルトップも見逃さない
ダブルボトムやダブルトップに比べてやや頻度は少ないものの、トリプルボトム・トリプルトップも反転の強いシグナルとして見逃せません。特に、3回目の試しで反発または下落に転じた場合は、方向性がより強く出る傾向があります。
トリプルボトムは、3度目の安値試しで反発し、強い買い圧力が確認できた時にエントリーのチャンスとなります。一方、トリプルトップでは3回目の高値試しで上抜けできず、売り圧力が高まる場面でショートを狙うのが基本です。
私自身も、レンジ相場の中でこうしたパターンが出現した際には、平均足の色変化と組み合わせてエントリーするようにしています。特に、1発目の反発が強いケースでは、その後のトリプル形成につながることが多く、意識して監視する価値があります。

トレンドが明確に出ていない時ほど、これらのチャートパターンはエントリーの手がかりになります。パターン形成の過程を冷静に見極めることが、勝ちパターンを増やす近道です。
上位足のトレンドと一致した順張りを徹底する
中期・長期の平均足で方向感を把握する
短期足だけを見てエントリーを判断すると、相場の大きな流れに逆らってしまい、思わぬ損失につながることがあります。これを防ぐためには、中期・長期の平均足を使って、全体の方向感をしっかり把握することが重要です。
なぜなら、上位足のトレンド方向に沿ってエントリーする「順張り」は、逆張りに比べて成功率が高く、リスクも低い傾向があるからです。たとえば、15分足や1時間足の平均足が青であれば、ロングを狙うべき環境。逆に赤であれば、ショート優位の相場と判断できます。
私もエントリー前には必ず、5分足・15分足・1時間足の平均足を確認するようにしています。上位足が赤なのに1分足の青だけを見てロングしてしまうと、戻り売りに巻き込まれて損切りになるケースが多いのです。

スキャルピングであっても、上位足の流れに逆らわない意識を持つことで、無理のないトレードが可能になります。エントリー前に「今、相場の大きな流れはどちらか」を必ず確認する癖をつけましょう。
ダブルボトムが機能しない「逆目線」の罠に注意
チャートパターンとして有効なダブルボトムですが、上位足のトレンドと逆方向に発生した場合は、機能しないことがあります。つまり、パターンの形だけを見て安易にエントリーすると、逆行によって損切りを余儀なくされる可能性が高まるということです。
私自身も、過去に上位足が赤(下降トレンド)であるにもかかわらず、1分足のダブルボトムを根拠にロングして失敗した経験があります。その時は、一時的に反発しても、すぐに上位足の売りに押されて下落してしまいました。
特に注意が必要なのは以下のような状況です。
- 上位足の平均足が強く赤くなっている
- トレンドラインや移動平均線が下向きに傾いている
- 高値が切り下がっている中でのダブルボトム出現
こうした局面では、反発の勢いが弱く、むしろ再度下落するための“だまし”となることが多いです。形にとらわれず、常に「どちらの流れが優勢か」を見極めることが、安定したトレードの基本になります。

チャートパターンは万能ではなく、相場の流れとセットで考えることが成功のポイントです。
利確ポイントは「直近ラインの手前」で設定する
利確が苦手な人がやりがちな失敗とその回避法
エントリーの精度が上がってきても、利確がうまくいかないと最終的に利益を残すことができません。特に初心者に多いのが、「利確ポイントを欲張りすぎて、利益を逃してしまう」ケースです。
なぜそれが失敗につながるのかというと、相場は直近の高値や安値で止まりやすく、そこを完璧に狙おうとすると反転に巻き込まれてしまうことが多いからです。エントリー後に利益が出ていても、そのまま戻されてしまい、最終的に建値決済や損切りになる……これは非常にありがちなパターンです。
私も以前は「せっかくなら天井まで取ろう」と考えてしまい、利確を逃すことがよくありました。しかし、いまでは直近ラインの2〜3pips手前で利確するように意識しています。それだけで利確成功率が大きく改善し、トータルの収益も安定してきました。
利確は「どこまで伸びるか」ではなく、「どこまでなら確実に取れるか」を基準に設定するのがコツです。反発の兆候が見えたら潔く手仕舞いするという姿勢が、勝ち残るためには必要です。
「頭と尻尾はくれてやれ」の具体的な使い方
利確判断に迷ったときに思い出したいのが、相場の格言「頭と尻尾はくれてやれ」です。この言葉は、相場の始まりと終わりを完璧に取ろうとせず、安全で確実な“中間部分”を狙うのが賢明だという教えです。
具体的には、直近の高値や安値が意識される価格帯に到達する“少し手前”で利確することを意味しています。たとえば、直近高値が145.00円なら、144.97〜98円あたりで利確するイメージです。これにより、直前の反転リスクを回避しつつ、しっかりと利益を確保できます。
私自身も、調子が悪いときほどこの考え方に立ち返るようにしています。高値や安値を意識しすぎて引っ張りすぎると、逆行して損切りになるケースが少なくないためです。

このように、「ちょっと手前で利確する」という謙虚な戦略は、トータルで見ればむしろ利益を最大化する手段となります。利確で悩む方は、まずこの格言を実践に取り入れてみてください。
スキャルピングでの連続エントリーを避けるべき理由
3回目エントリーの勝率が下がる心理的・波動的要因
スキャルピングで一度うまくいくと、つい勢いに乗って何度もエントリーしてしまいたくなります。しかし、特に3回目のエントリーでは勝率が一気に下がる傾向があります。これは単なる偶然ではなく、心理的・相場的な背景に明確な理由があるのです。
まず、心理面では「連勝の気持ちよさ」によって判断が甘くなりがちです。勝ちが続くと、「次もいける」と過信してしまい、根拠のないポジションを取りがちになります。また、損失を避けたいあまりに利確や損切りが遅れ、逆行による損失を膨らませる原因にもなります。
相場構造の面では、エリオット波動などの観点から見ても、価格は「1〜3波」で大きな動きが出て、その後は反転・調整に入る傾向があります。つまり、3回目のエントリーは、ちょうど相場が休憩に入るか反転するタイミングと重なりやすいというわけです。
私も初心者の頃は、連勝のあとの3回目で大きく損失を出してしまうことがよくありました。今では「1日2〜3回まで」とルールを決め、調子が良くても淡々と終えるようにしています。

連続エントリーは一見効率的に見えますが、実際にはリスクが高く、勝率も下がる行動です。自制心を持って回数を絞ることで、トータルの収支は安定します。
1日2〜3回に絞ることで安定して利益を残す
スキャルピングはスピード感のあるトレード手法ですが、それゆえに「回数を増やせば儲かる」と思われがちです。しかし実際には、1日のエントリー回数を2〜3回に絞ったほうが、結果として安定した利益を残しやすくなります。
理由は明確で、トレードは体力や集中力、判断力が問われる作業であり、回数が増えるごとにその質が下がっていくからです。最初の1〜2回は冷静にチャートを分析できても、3回目以降は「とにかく入りたい」という欲が出てきて、無理なエントリーにつながってしまいます。
私自身も、1時間程度のスキマ時間の中で2〜3回のチャンスを見極めてトレードすることを基本にしています。その方が気持ちにも余裕が持てますし、負けた場合のリカバリーも冷静に行えるからです。
エントリーは多ければ多いほどいいわけではありません。「この1回に集中する」という意識が結果につながります。トレードにおける“質と量のバランス”を意識して、必要以上に回数を重ねないことが、継続的に勝ち残るための大きなポイントです。
インジケーターと時間帯の使い分けで精度を高める
3連MACDとRCIを使った初動エントリー手法
チャートパターンや平均足に加え、インジケーターを組み合わせることでエントリーの精度はさらに高まります。中でも、私が実際に使っていて効果を感じているのが「3連MACD」と「RCI」の併用です。
3連MACDとは、異なる3つの時間軸に設定したMACD(たとえば1分足・5分足・15分足など)を一括で表示できるインジケーターです。この3つがすべて同じ方向を示していれば、相場に明確なトレンドが出始めているサインと考えられます。たとえば、全てがゴールデンクロスを示している場面では、買いの初動を捉えやすくなります。
また、RCIを併用することで、トレンドの勢いだけでなく“タイミング”も見極めやすくなります。特に、短期RCIが反転し、中期・長期と揃ってくるタイミングは、エントリー根拠として非常に有効です。
私自身も、平均足の色変化だけで判断するのではなく、3連MACDとRCIの一致を確認してからエントリーしています。これにより、根拠が明確になり、判断がぶれにくくなりました。
インジケーターは“補助ツール”として活用することで、裁量トレードの再現性が高まり、ミスを減らすことにもつながります。

特に初心者の方には、この2つの組み合わせを取り入れることをおすすめしたいと考えています。
東京・欧州・ニューヨーク市場の特徴を理解する
スキャルピングで安定した成果を出すには、時間帯ごとの市場の特性を理解しておくことが重要です。市場によって値動きの性質が異なり、それに合った戦略を取らなければ、本来機能するはずの手法でも損失につながってしまいます。
それぞれの市場には、以下のような特徴があります。
- 東京時間(9:00〜15:00)
値動きは全体的に穏やかで、ボラティリティが低め。レンジ相場になりやすく、反発狙いの戦略が向いています。 - 欧州時間(16:00〜21:00)
取引量が一気に増え、ブレイクが発生しやすい時間帯。トレンドの初動が出やすいため、順張りを意識したエントリーが有効です。 - ニューヨーク時間(22:00〜翌2:00)
世界的に最も取引量が多く、ボラティリティも最大化される時間。トレンドの継続性が強く、値幅を狙いやすい局面が多くなります。

私自身も、東京時間では無理にトレンドを狙わず反発型に切り替え、欧州・NY時間にトレンド狙いを集中させるようになってから、負けトレードが減りました。市場の特徴に合わせた戦略選びが、安定した勝ちにつながります。
時間帯ごとの平均足挙動と適切な戦略の違い
平均足はトレンドの強弱を視覚的に捉えやすい便利なツールですが、その挙動は時間帯によって異なります。よって、平均足の“見方”と“使い方”も時間帯に応じて調整することが不可欠です。
以下に、時間帯別の平均足挙動と有効な戦略をまとめます。
- 東京時間
平均足の色が頻繁に切り替わり、ひげも多く出る傾向があります。このため、だましに遭いやすく、反発型やチャートパターンの完成を待ったエントリーが有効です。 - 欧州時間
平均足が連続して同じ色を保ちやすくなり、トレンドが伸びやすい時間帯です。色変化の2〜3本目を狙う順張り戦略が適しています。 - ニューヨーク時間
トレンドの継続性が最も高まり、平均足の色変化をそのまま信じて入る戦略が効果を発揮します。特に、経済指標や市場オープン直後は一方向に大きく伸びることも多く、積極的に狙いたい時間帯です。

私も時間帯に応じて平均足の見方を切り替えることで、無駄なエントリーを減らせるようになりました。「平均足はいつでも同じように使えるわけではない」という視点を持つだけで、勝率は確実に上がります。
感覚ではなく「根拠のある型」を持つ
短時間で効率よく利益を上げたいと考えるスキャルパーにとって、感覚ではなく「根拠のある型」を持つことが何より重要です。今回ご紹介したように、平均足の色変化やチャートパターン、直近の高値・安値のライン、上位足との整合性、そして時間帯別の特性を理解していれば、1日2〜3回のトレードでも十分に安定した成果を出すことが可能です。
私自身も、こうした要素を一つずつ積み上げることで、初心者の頃から安定的に勝ちトレードを増やすことができました。特に大切なのは、「勝ちパターンを見つけて再現する」ことと、「時間帯や環境によって戦略を切り替える柔軟さ」です。
焦って無理にトレード回数を増やしたり、直感だけでエントリーしたりすると、一時的に勝てたとしても長くは続きません。だからこそ、自分の得意な型を持ち、それを守る姿勢がトータルの勝率を押し上げてくれます。
まずは1時間〜2時間のスキマ時間でも構いません。今回の内容を参考に、チャートを「戦略的に」見てみてください。そして、少しずつでも自分のスタイルを固めていきましょう。

1年後に継続して勝てるトレーダーになれるよう、無理せず焦らず、一緒に取り組んでいきましょう。