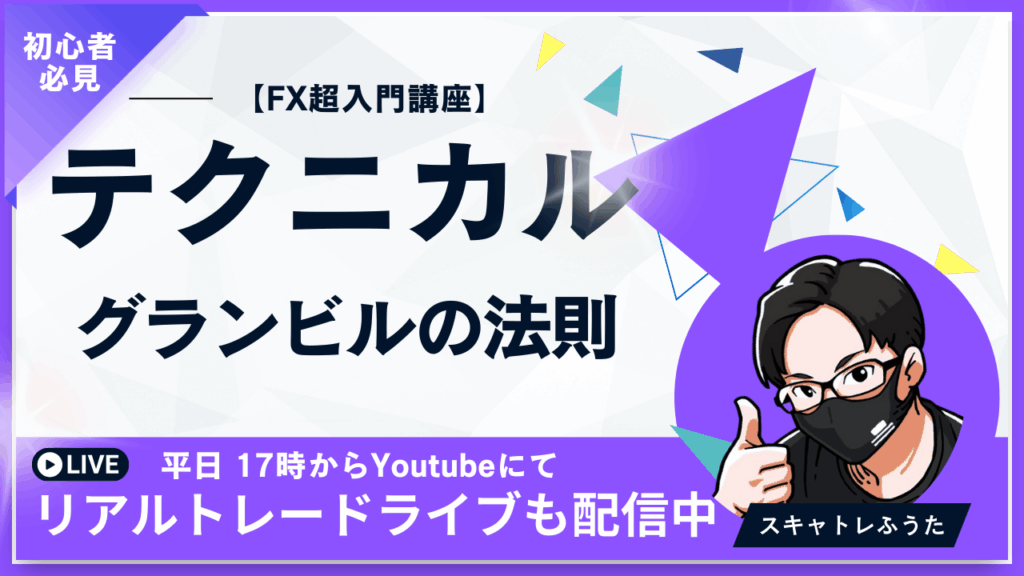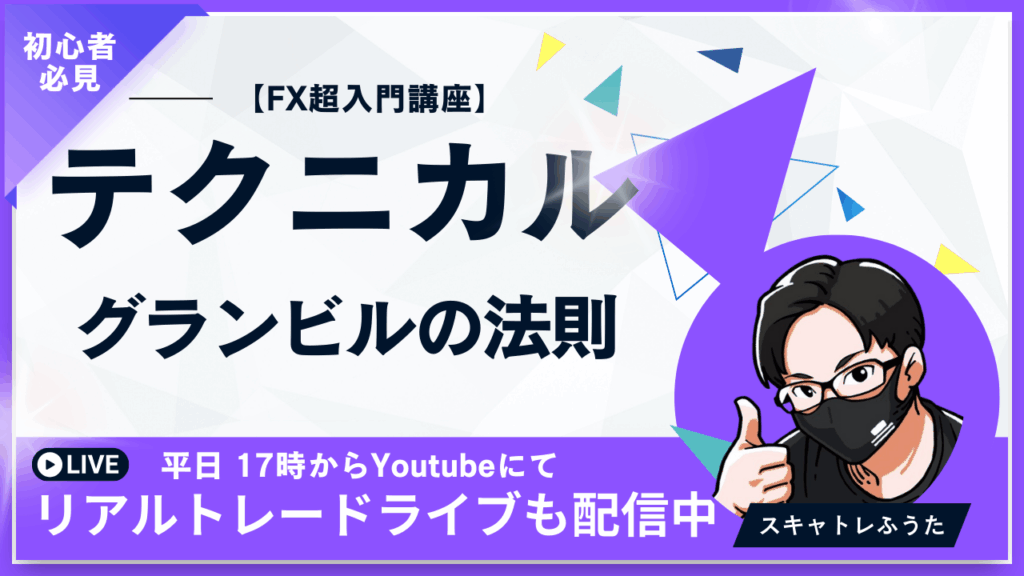
FXトレードで相場の流れを掴むには、基礎的な理論を理解するだけでなく、それを実践に落とし込む技術が欠かせません。その中でも「グランビルの法則」は、移動平均線と価格の関係をもとに、トレンドの転換点や継続の兆しを判断するうえで非常に有効な指標です。
この法則を使いこなせるようになると、ドル円やポンド円といった通貨ペアでのエントリーや決済がより明確になり、優位性のあるトレードが可能になります。
また、ダウ理論やエリオット波動と組み合わせることで、相場の全体像まで読み解く視点が持てるようになる点も大きな利点です。
本記事では、グランビルの法則の基本構造から、買い・売りそれぞれの活用パターン、さらに他の理論との融合による実践的な応用法までを段階的に解説していきます。

トレードの再現性を高めたい方は、ぜひ最後までお読みください。
これからFXを始める初心者に観てほしい動画です。
グランビルの法則とは|相場の規則性を捉える基本理論
移動平均線と価格の関係から読み解く8つのパターン
グランビルの法則とは、移動平均線の形状と価格の位置関係から、相場の転換点やトレンドの継続を8つのパターンで示した理論です。買いの4パターン(1〜4)と、売りの4パターン(5〜8)に分類されており、それぞれがチャート上での判断材料になります。
特に注目すべきは、移動平均線の向きが変化するタイミングです。下落から横ばい、そして上昇へ転じた場合には買い、上昇から横ばい、そして下落へ転じた場合には売りのサインが出やすくなります。
つまり、移動平均線そのものが「相場の傾き」を教えてくれる指標となり、それに対する価格の動き方がグランビルの8パターンとして整理されているのです。
この法則を知ることで、単に「上がっているから買う」「下がっているから売る」といった曖昧な判断ではなく、根拠を持ったタイミングでトレードが可能になります。
ダウ理論・エリオット波動との共通点と違い
グランビルの法則を活用する上で重要なのは、ダウ理論やエリオット波動との組み合わせです。
なぜなら、これらの理論はそれぞれ異なる角度から相場の構造を捉えているものの、実際のチャート上では一致する局面が多いからです。
たとえば、グランビルでいう第2の買いシグナルは、ダウ理論での「安値切り上げ」、エリオット波動での「第3波の起点」と一致しやすい場面です。こうした視点を重ねて見ることで、「今はトレンドがどの段階にあるか」が立体的に見えてきます。
グランビルは移動平均線をベースにした「視覚的なタイミング判断」に強みがあり、トレンドの転換や継続を比較的シンプルに捉えられるという利点があります。
一方、エリオット波動は波の数を数える構造分析、ダウ理論は高値・安値の切り上げ下げに注目したトレンド分析という違いがあります。

それぞれの理論を独立して使うのではなく、融合して活用することで、より精度の高いトレード判断が可能になります。
買いエントリーを判断する3つのタイミング
第1の買い|移動平均線の上抜けは初動サイン
グランビルの法則における「第1の買い」は、移動平均線が下落から横ばいを経て上向きに転じ、価格がそれを下から上に抜けた場面です。これはいわゆるトレンド転換の初動にあたり、相場が上昇に切り替わる可能性を示しています。
ただし、ここで重要なのは「初動=タイミングが難しい」という点です。チャート上では一見チャンスに見えますが、反転の見極めが難しく、だましの動きに巻き込まれやすい場面でもあります。
私自身も初心者の頃、この初動で何度も早すぎるエントリーをしては失敗を繰り返していました。
そのため、グランビルの第1パターンは「トレンド転換の兆しを確認する場面」として意識し、エントリーは見送り、次の動きを待つのが現実的です。
エリオット波動で言えば第1波に相当しますが、まだ方向感に確信を持てない段階ですので、無理に攻める必要はありません。
第2の買い|押し目買いは安値切り上げとセットで狙う
グランビルの法則の中で、最も信頼性が高く、実際のエントリーでもよく活用するのが「第2の買い」です。これは、移動平均線が上向きの状態で価格が一度下落し、再度反発して移動平均線を下から上に抜けたポイントに該当します。
このパターンでは、チャート上で「安値切り上げ」が確認できることが多く、ダウ理論でも上昇トレンド継続のサインと一致します。さらに、エリオット波動で言えば「第3波の入り口」として捉えることができるため、トレンドが強く出やすい局面です。
私もこの第2パターンは積極的に狙うようにしています。ただし、ネックライン(直近高値)を超えた直後にエントリーするよりも、安値切り上げが確認できたタイミングで先回りする方が、リスクリワードの面でも有利です。
押し目買いを意識する際は、以下の3点をセットで確認すると、より安定したエントリーにつながります。
- 移動平均線が上向きであること
- 直近安値を割っていないこと
- 再上昇の勢いがあること

このようなチェックポイントをあらかじめ整理しておくことで、迷いの少ないトレード判断が可能となります。
第3の買い|トレンド継続局面での順張り戦略
「第3の買い」は、すでに移動平均線が上向きの状態で、価格がその近辺まで下落したものの、割り込むことなく再び上昇していく局面です。
これは、トレンドが継続している中での押し目となり、順張りの好機といえるパターンです。
この局面はエリオット波動でいう「第5波」にあたり、すでに相場は十分に上昇している段階です。そのため、初心者にとっては「高値掴みになるのでは」と不安に感じるかもしれませんが、トレンドが強いときにはこのような場面でもしっかり伸びていくことがあります。
重要なのは、ここで「売り目線にならないこと」です。すでに移動平均線が上向きである以上、反発しやすい環境にあると判断できます。実際に私も、このパターンで無理に逆張りして負けるケースを見てきました。

順張りを意識してエントリーする際は、「勢いが残っているか」「直近の高値を更新し続けているか」などを見ながら、伸び代のあるトレンドに乗ることが大切です。
売りエントリーを見極める3つのシグナル
第4の売り|移動平均線の下抜けは転換初動の兆し
グランビルの法則における「第4の売り」は、移動平均線が上昇から横ばい、そして下向きに転じたタイミングで、価格が上から下へ抜けた場面です。これは相場が下落トレンドに入る可能性を示す、いわば「転換初動」のサインにあたります。
一見すると売りのチャンスに見えますが、実際には非常に判断が難しい場面です。なぜなら、この段階ではまだ高値圏で下げ渋る可能性があり、思ったように下落が続かないケースも多いためです。私自身もこの初動で焦ってエントリーし、反発に巻き込まれて損切りした経験が何度もあります。
特にロング目線の人にとっては心理的なストレスも大きく、「まだ上がるのでは?」という迷いが入りやすくなります。そのため、この第4パターンは無理に攻めず、トレンドの転換がより明確になるまで様子を見ることをおすすめします。
第5の売り|戻り売りは高値切り下げとセットで判断
「第5の売り」は、移動平均線が下向きの中で価格が一旦上昇し、その後再び移動平均線を下抜けた場面です。これは「戻り売り」の典型的な形であり、売り戦略の中でも最も信頼性が高いパターンの一つです。
この局面では、ダウ理論でいう「高値切り下げ」、エリオット波動でいえば「下降第3波の入り口」と重なることが多く、強い下落が期待できる局面です。実際に私も、このパターンでは積極的にエントリーすることが多く、成功率も比較的安定しています。
ただし、価格が移動平均線を一時的に上抜けることもあるため、チャートをよく観察し、「どのタイミングで再度下落に転じるか」を見極めることが重要です。高値が更新されず、ローソク足が再び移動平均線の下に戻ってきたところが狙い目です。
このような戻り売りは、トレンドが継続している証でもあり、次のような条件を確認することで、売りの信頼性が高まります。
- 高値が更新されずに頭打ちしていること
- ローソク足が再び移動平均線の下に戻ってきていること
- 全体として下向きのトレンドが継続していること
こうした複合的な根拠がそろった局面では、自信を持ってエントリーできるようになります。
第6の売り|レジスタンスとしての移動平均線に注目
「第6の売り」は、価格が上昇して移動平均線に近づくものの、それを越えられずに再び下落するパターンです。このとき、移動平均線がレジスタンスとして機能している点が大きな特徴です。
この場面は、すでに相場全体が明確に下降トレンドにあり、戻りも限定的に終わる傾向があります。私も過去に、この移動平均線が「壁」となっている場面を確認しながら売りで入ることで、比較的スムーズに利を伸ばせた経験があります。
このとき注意すべきなのは、「全戻し」のように上昇した分をすべて打ち消すような強い売りが入っているかを確認することです。特に上位足でも同様の動きが確認できれば、複数の時間軸で下降圧力がかかっている証拠となり、売りの信頼性が高まります。
つまり、第6のパターンでは「移動平均線が超えられない=売りが強い」という構図を読み取り、反転の勢いに乗ることがポイントになります。
グランビルの法則と他の理論を融合させる視点
ダウ理論との併用でトレンド構造を明確にする
グランビルの法則をより効果的に使うには、ダウ理論との併用が欠かせません。なぜなら、ダウ理論はトレンドの基本構造を「高値・安値の切り上げ/切り下げ」という視点から明確に示してくれるからです。
たとえば、グランビルの第2の買いは、移動平均線の上抜けとともに、安値が切り上がっていることが多く、これはダウ理論の「上昇トレンド継続」のサインと一致します。
第5の売りでは、高値切り下げが同時に発生し、下降トレンドが再加速する局面と見なせます。
実際のチャート分析では、グランビルだけで判断するよりも、「ダウ理論でトレンドの方向性を確認→グランビルでタイミングを見極める」という順序で見ていくと、エントリー・決済判断が明確になります。

このように、ダウ理論とグランビルの法則を組み合わせることで、トレンドの背景とエントリーポイントの両方に根拠を持てるようになり、判断に迷いが少なくなります。
エリオット波動と重ねて波の強弱を見極める
もう一つ有効な組み合わせが、エリオット波動との融合です。エリオット波動は、相場を5つの上昇波と3つの修正波に分解し、それぞれの段階でどの程度の勢いがあるかを捉える理論です。
たとえば、第2の買いはエリオット波動でいう第3波に対応するケースが多く、強いトレンドの中でエントリーするチャンスを示します。一方で第3の買いは第5波、つまり上昇の終盤であることが多いため、「このトレンドはどこまで続くか?」という視点で見極めが必要です。
私自身、トレード判断の際には「今が第何波か?」を考えながら、グランビルのパターンと重ねて確認するようにしています。そうすることで、エントリーの勢いがどの程度あるかを把握でき、無理な逆張りを避けることができます。
グランビルの法則がタイミングの可視化に優れている一方、エリオット波動は相場全体の構造や波の強弱を補完してくれる理論です。この2つを組み合わせることで、相場の中で「どこを攻めるべきか」「どこで様子を見るべきか」がはっきりと見えてきます。
相場の全体構造から判断精度を高めるには
上位足の流れを確認しながらエントリー判断をする
グランビルの法則を活用する際、重要な前提となるのが「どの時間軸で相場を見ているか」という視点です。トレードにおいては、1分足や5分足といった短期足だけを見て判断するのではなく、15分足・1時間足・4時間足といった上位足の流れを把握することが、判断の精度を大きく左右します。
たとえば、5分足でグランビルの第2の買いパターンが出ていても、上位足で下降トレンドが継続している場合、買いが失速してしまう可能性があります。逆に、上位足でも安値切り上げの流れが確認できれば、より強い根拠をもって買いで攻めることができます。
私も実践の中で、上位足の環境認識を取り入れるようになってから、トレードの失敗が減り、無駄な逆張りも自然と減っていきました。

グランビルの法則は、チャートの「今ここ」の状況を判断する手段ですが、「全体の流れの中でどこにいるか」を把握することで、その判断がより効果的に機能するようになります。
無理な逆張りは避け、確度の高い波に乗る意識を持つ
相場には常に「上がるか、下がるか、もみ合うか」の3つの状態がありますが、多くのトレーダーが失敗するのは、「高値だから売る」「下がったから買う」といった逆張り思考に陥ることです。
グランビルの法則を正しく使うためには、「トレンドに乗る意識」を常に持つことが大切です。特に第2の買いや第5の売りなど、トレンドに沿ったエントリーポイントでは、勢いが継続しやすく、勝率も安定しやすい傾向にあります。
逆に、初動の第1や第4のパターンは転換点であるがゆえに判断が難しく、慣れないうちは手を出さない方が無難です。私自身も、以前は高値圏で無理にショートを仕掛けて失敗した経験がありますが、順張りを徹底するようになってからは大きな損失が減りました。
順張りを徹底するためには、次のような意識を持つことが重要です。
- トレンド方向に沿ったエントリーポイントを狙う
- 第2の買いや第5の売りなど、信頼性の高い局面に絞る
- 初動パターン(第1・第4)では無理に入らない

「確度の高い波にだけ乗る」という意識を持つことで、トレードの再現性が高まり、精神的なストレスも軽減されます。
初心者がグランビルの法則を使いこなすための考え方
初動は狙わず、確度の高い局面に集中する
初心者がグランビルの法則を使う上でまず意識すべきは、「すべてのパターンを狙おうとしない」ことです。特に第1の買いや第4の売りのような“初動”のシグナルは、トレンド転換の最初の動きであり、だましも多く、タイミングの判断が非常に難しいポイントです。
これらは、経験を積んだトレーダーが状況を見極めたうえで入るべき局面であり、初心者が無理に入ろうとすると、むしろトレードを不安定にしてしまう原因になります。
私自身も初期の頃は、動き出しそうなチャートを見るたびに飛びつきたくなっていましたが、「第2の買い」「第5の売り」など、トレンドがすでに出ていて、かつ押し目や戻りが確認できる場面に絞るようになってから、トレードの精度が大きく改善しました。

まずは、確度の高い場面だけに集中する。それがグランビルの法則を安全かつ効果的に活かす第一歩です。
「知らない」状態から学び続ける姿勢が成長のコツ
グランビルの法則を含め、FXの理論を最初から完璧に理解することは不可能です。重要なのは、今の自分にとって「知らない」「まだ見えていない」という前提を受け入れ、そこから少しずつ学び続ける姿勢を持つことです。
私自身、当初は誰にも教わらず独学で試行錯誤を繰り返してきました。振り返ってみると、知識を一気に詰め込もうとするよりも、「あ、この場面が第2の買いだったのか」と、過去のチャートを見て一つひとつ気付いていく過程が最も成長につながっていました。
初心者の段階で焦りは禁物です。焦って勝とうとすると、負けたときに大きく崩れてしまいます。むしろ「今日はこのパターンを見つけよう」「今のトレンドはどの段階にあるかを確認しよう」といった目標を持ってチャートを観察していく方が、自然と分析力が磨かれ、実践に活かせる知識が蓄積されていきます。
トレードは「理解」から始まり、「実践」「気付き」「成長」という流れで進んでいきます。グランビルの法則も、その一連のプロセスの中で少しずつ使いこなせるようになりますので、焦らず地道に続けていきましょう。
グランビルの法則を活かすためのトレード実践アドバイス
エントリー精度はチャートの「気付き」から生まれる
グランビルの法則を実践で活かすためには、ただパターンを覚えるだけでなく、「今のチャートがどの局面にあるか」を自分自身の目で見抜けるようになることが重要です。つまり、理論を知っているだけでは不十分で、日々のチャート観察を通じた“気付き”があってこそ、エントリーの精度が高まっていきます。
私も経験上、グランビルの8パターンをすぐに使いこなせたわけではありません。最初は「どこが第2の買いなのか?」「これは第5の売りに該当するのか?」といった疑問ばかりでした。しかし、過去チャートを何度も検証し、繰り返し「このパターンが出たときの結果はどうだったか」を検証する中で、徐々に判断が定着していきました。
気付きは一朝一夕では得られませんが、自分のトレードの中で何度も同じ場面に遭遇することで、感覚として掴めるようになります。

グランビルの法則も、机上の理論として終わらせず、「チャート上のリアルな動きと結びつけること」が上達の近道です。
焦らず積み上げることで相場分析力が身につく
FXにおいて結果を急ぐあまり、無理なトレードを繰り返してしまう方は少なくありません。しかし、グランビルの法則をはじめとした分析手法は、一つひとつの理解と経験の積み重ねによって初めて効果を発揮するものです。
焦りは判断を曇らせ、必要のないエントリーや、根拠の薄いポジションにつながります。私自身も以前は「早く利益を出さなければ」という気持ちから無理にポジションを持ち、損失を膨らませてしまったことが何度もありました。
しかし「今日は1つだけ明確な場面を見つけよう」「負けても良いからルール通りにやってみよう」と意識を変えたことで、次第に相場の全体構造が見えるようになり、トレードに自信が持てるようになりました。
グランビルの法則は、そうした積み上げの中でこそ力を発揮します。今日すぐに勝てなくても、毎日一歩ずつ経験を積み重ねることで、自然と相場の読み方が洗練されていきます。

焦らず、自分のペースで続けていきましょう。
まとめ
グランビルの法則は、移動平均線と価格の関係から相場の転換や継続を判断するための基本的かつ強力なツールです。その8つのパターンを正しく理解することで、ドル円やポンド円のような通貨のエントリーポイントや決済の目安が見えてくるようになります。
しかし、ただパターンを覚えるだけでは十分とはいえません。ダウ理論やエリオット波動と組み合わせ、全体のトレンド構造を把握したうえで、グランビルのシグナルを使いこなすことが大切です。
さらに、初動ではなく「確度の高い局面」に絞ってエントリーすることが、初心者にとっては最も安全かつ効果的な戦略となります。
理論を理解し、実際のトレードで試しながら、日々のチャート観察を通じて得られる気付きを積み重ねていく。この繰り返しこそが、グランビルの法則を実践で使いこなす力へとつながります。

焦らず、目の前のチャートと丁寧に向き合いながら、グランビルの法則をあなたの武器として育てていってください。